| ニッポン観光ペナント展示館 | 8 湖・湿原 1 |
| こちらでは、湖と湿原のペナントを展示いたします。枚数が多いため二つの展示室に分割されますが、内容上の分類ではありません。 |
1 原生花園(北海道・斜里郡 1980年)P
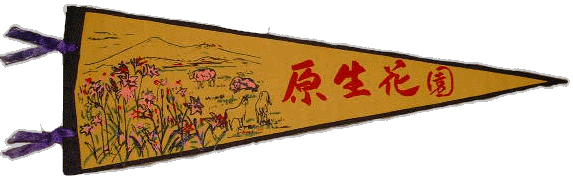
210x639mm、布に印刷、赤のみ繊維印刷、1980年9月4日、国鉄・網走駅前「モヨロ民芸」にて購入、価格不明。
「原生花園」の地名は日本各地に存するが、これは北海道斜里郡小清水町の「小清水原生花園」のものである。一見しただけでは、そこに行った本人か、説明を受けなければどこかわからないのが少々残念ではある。しかし、牛が放牧されている様子や、背景の山・斜里岳の稜線は特徴がよく出ていて、旅行好きの人ならばわかるかもしれない。
黄色地に黒の輪郭線、赤の繊維印刷による地名ロゴと、ピンク・緑のインク印刷によるデザインはリアルではないが手作り然としたほのぼのぶりがよい感じである。これを安っぽいと感じるか、懐かしく感じられるか、評価は分かれるだろう。
なお、リボンを通す穴には、画像ではわかりづらいと思うが、黒を塗装した鉄の輪環がちゃんと付されている。
2 尾瀬 4点(群馬・福島県 1978年)すべてP
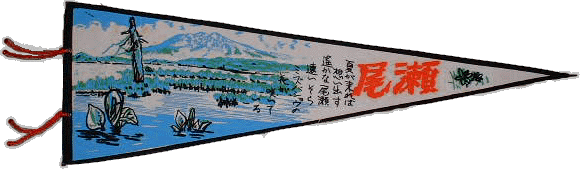 a
a203x645mm、布に印刷、枠線を含む黒が繊維印刷で、赤・青・緑はインク印刷。1978年7月21日、尾瀬ヶ原「温泉小屋」にて購入、200円。
前褐の「原生花園」に比べれば、実にリアルである。さわやかな尾瀬のイメージが簡素に、コンパクトにまとめられている。前景となるミズバショウの花と湿原、朽ちた立ち木、そして遠景の燧ケ岳まで、青と緑の2色だけで描かれていて、一種の透明感をかもし出す。三角の右端に書き添えられた花は、その輪郭からおそらくニッコウキスゲだと思われるが、ミズバショウの花の花芯とあわせて黄色を使っていればもう少し雰囲気が出たようにも思える。しかし、青・緑の2色で十分まとまっているのだから、生産コストを考えればこれはこれでよかったのかもしれない。
ダメ押しで、尾瀬といえばこの歌というべき有名な詩の一節が添えられていて、雰囲気を盛り上げている。
 b
b195x558mm、布に印刷。1978年7月22日、長蔵小屋にて購入、100円。
黄色地に赤と黒の2色印刷で、「原生花園」以上にシンプルである。小さめのサイズ、英字ロゴ、ミズバショウと湿原・燧ケ岳、ピッケルをレイアウトしたデザインは、観光ペナントというより、山岳ペナントの雰囲気が強い。黒に赤で影(立体感)をつける「OZE」のロゴデザインも独特である。
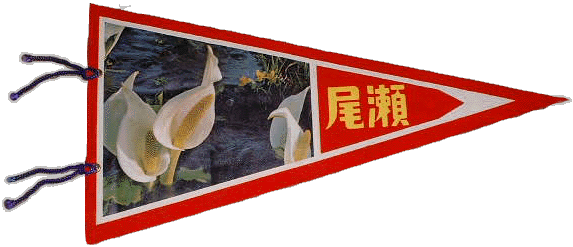 c
c223x440mm、1978年7月21日、温泉小屋にて購入、150円。
ビニル製の素材が珍しい。表面は布のような質感を出すため、ざらざらの加工がなされている。赤い部分は繊維印刷で、残りはインク印刷である。
一見して写真ペナントの特徴を備えているけれども、サイズがとても小さい事、ビニル地に繊維印刷を施す事など、決定的に成り立ちを異にしていると言えよう。写真ペナントに繊維印刷をする例は、数は少ないが他に例がある(後出)。
尾瀬のペナントであるが、その写真は当地の代名詞というべきミズバショウに絞り込んでいて、可愛らしい出来になっている。
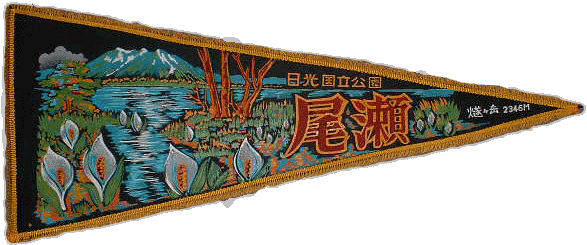 d
d290x713mm、布に印刷、1978年7月21日、温泉小屋にて購入、250円。
色使い、イラストの特徴、地名ロゴにおいては製版ミスかと思われるような輪郭と中塗りが一致しない点など、前褐の「AKAGI(4 山Ⅱ-8」・「美ヶ原高原(5 高原・峠-4)」とまったく同じである。このペナントにはパッケージの紙のタグが付いていて、「秀作ペナント」と銘打たれている。「秀作ペナント」は、当展示館ではあと「富士山a(3 山Ⅰ-4)」がそれである。これらは当然同じメーカーのものだろう。いずれも黒地に細密な配色を施し、素朴な味のイラストを特徴とする。
ペナントに「燧ケ岳2346M」と入っているので遠景の山はそれだと理解されるが、言われなければ至仏山かと思われる程なだらかな山容に描かれている。しかしこれは、素朴な味のイラストにあわせた一種のデフォルメというべきものなのだろう。
3 白樺湖(長野県 1980年)P
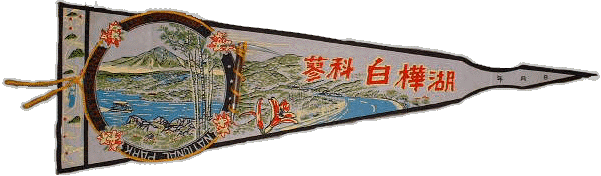
216x689mm、布に印刷、1980年5月、蓼科牧場・旅館つつじ荘にて購入、価格不明。
展示順にここまで来られた方ならば、このペナントがいわゆる「デラックスペナント」で、先の「蔵王」や「上高地」とまったく同じ特徴を備えていることがおわかりであろう。くわしくは繰り返さない。このペナントにおいて先の例と明らかに違うのは、三角の左端に簡単なイラストマップを付している点である。
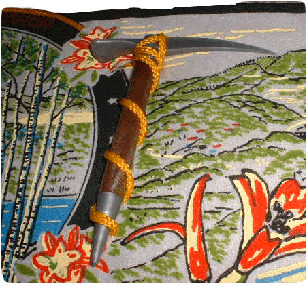
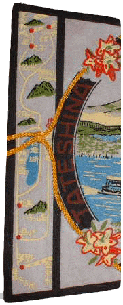
地図は白地にクリームイエローで印刷されているので非常に読み取りづらいが、蓼科の簡単なロードマップになっている。
イラストは、蓼科山と白樺湖、ビーナスラインにニッコウキスゲの花を配して鮮やかだ。ピッケルのすぐ右の山腹に赤いものが点在するのは、旅館街の屋根だろうか、実に細かな描き込みぶりである。
4 富士五湖(山梨県 1970年代後半?)☆P

264x684mm、紙に印刷、価格不明。パッケージの紙タグに、「ペガサスカラー」のマーク入りである。このマークは、当展示館内に散見され(後出)、「パッケージ・お土産包装紙コレクション」のページでまとめられる。
房(黄色)は、ナイロン編みの紐タイプではなく、さらさらとしたビニルである。
「富士五湖」のロゴデザインと、右端の日付記入欄のデザインが「妙高高原(5 高原・峠-5)」とまったく同じであるので、「妙高高原」も「ペガサスカラー」であったと思われる(「妙高高原」のパッケージは遺失されている)。地名ロゴのバックは、「妙高~」が青ベタであったのに対して、こちらはチェック柄とおしゃれだ。
さて、写真は五湖のうちのひとつに絞った内容である。これは何湖か。ヒントは富士山の稜線にある。わずかながら、宝永火山の稜線が左に写り込んでいることから、五湖のうちもっとも東寄りの湖であることがわかるであろう。中山湖である。右から陸地がせり出しているので、地図を確認すれば撮影地点がほぼピンポイントで特定できる。わずかな積雪の瞬間を狙った美しい写真を使用していて、絵はがき写真としても完成度の高い写真ペナントであると言えよう。
5 野尻湖(長野県信濃町 1970年代後半?)☆P

221x593mm、綿に印刷、価格不明。
一見して、シルクスクリーンの版画のようなイラストの味が珍しい。観光ペナントの中でも、異色というべき垢抜けた雰囲気が印象的な一枚である。また、左端の茶色のタグは、合成皮革製であり、これも当展示館においては他に例のないデザインである。三角の全体をひとつのイラストで埋めてしまうレイアウトも珍しいと言える。青・緑のイラストにオレンジ色の地名ロゴを組み合わせて、実に鮮やかな一枚である。
| ページトップへ インフォメーションに戻る |